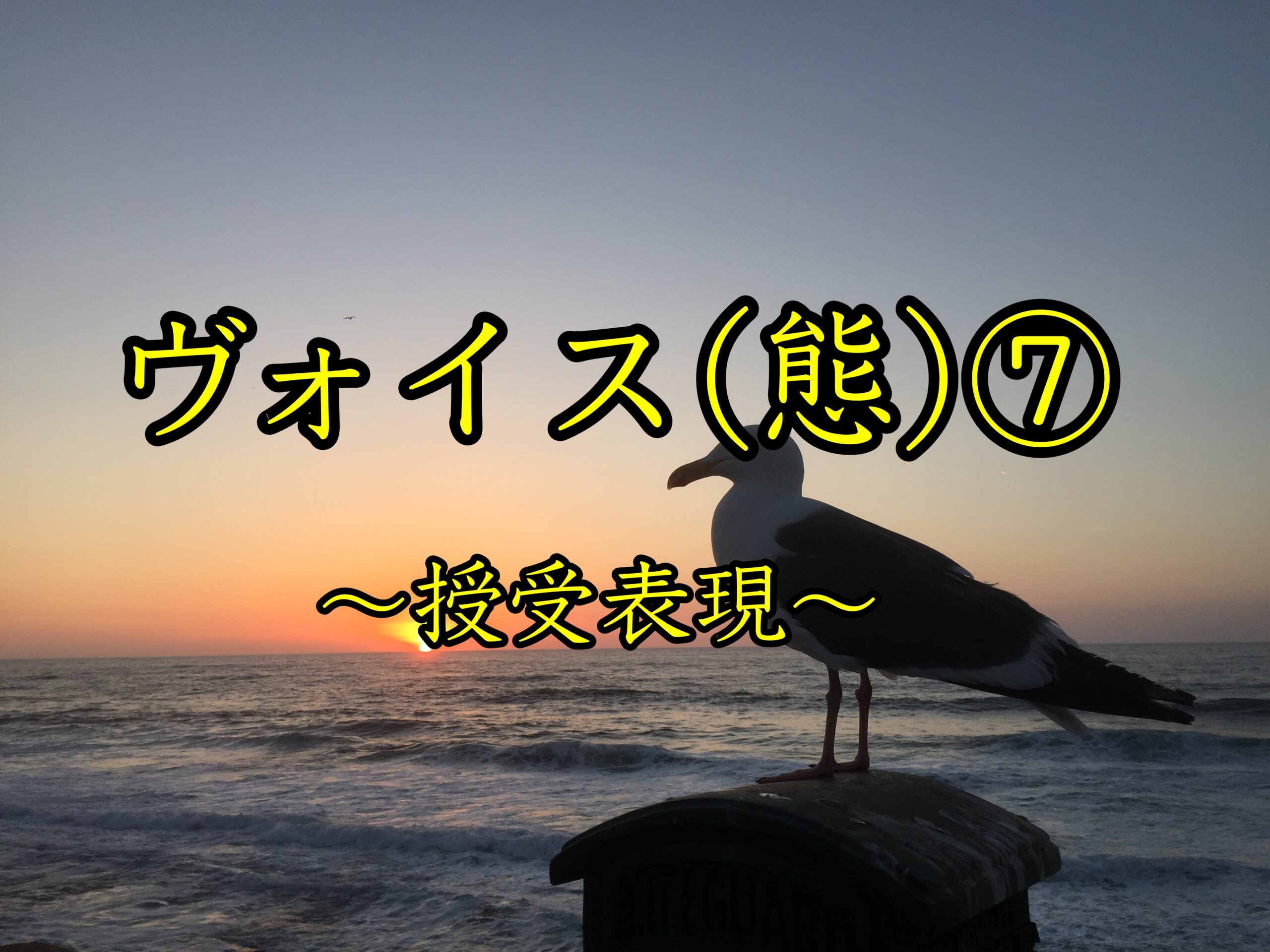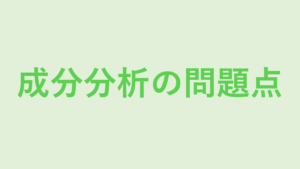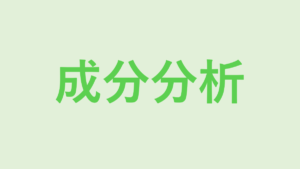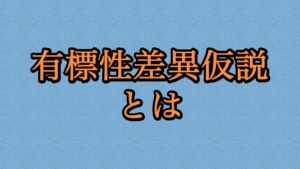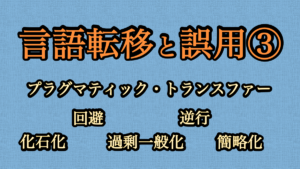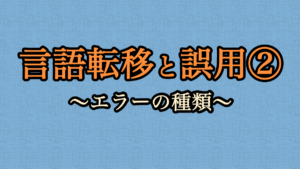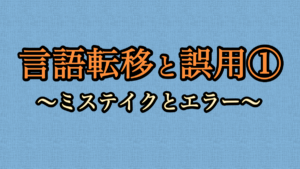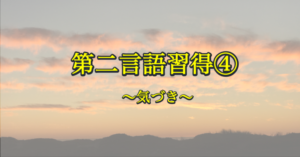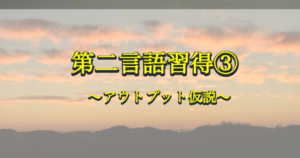今回は授受表現です。
授受表現は教材によっては態に含まれていないこともあるのですが、今回は態として扱います。
授受表現とは
授受表現とはその名の通り、物や動作の授受を表します。
難しい言葉で言ってもしょうがないので、簡単に言うと、「あげる」「もらう」「くれる」の3つの言葉のことです。具体的な言葉を聞くととても簡単に思えます。
しかし、学生にとってはとても複雑です。
物の授受と恩恵の授受の2つの用法に加え、3つの使い分けが非常に大変になるからです。
それぞれ順番に見ていきましょう。
物の授受
物の授受とはプレゼントをあげたり、お金をもらったりするような、物のやりとりのことです。
特徴は「あげる」「もらう」「くれる」が単独で動詞として使われます。
・(私が)友達にプレゼントをあげた。
・(私が)両親に時計をもらった。
・おじいちゃんが(私に)お小遣いをくれた。
このようなものが簡単な例です。
「プレゼント」「時計」「お小遣い」のような物がやり取りされているのがわかります。
恩恵の授受
一方で、恩恵の授受とは、行為のやりとりのことです。
行為のやりとりと聞いてもあまりピンとこないかも知れませんが、例を聞くとわかりやすいと思います。
・私が恋人にプレゼントを買ってあげる。
・兄に宿題を手伝ってもらう。
・親切な人が荷物を持ってくれた。
このようなものです。
特徴としては、「あげる」「もらう」「くれる」が単独では使われておらず、他の動詞といっしょに使われています。
「買う」「手伝う」「持つ」という動詞のテ形に接続していますね。
使い分け
先ほど使い分けが複雑だと紹介しましたが、なぜ複雑なのか簡単に触れておきます。
英語の話になってしまいますが、英語には授受の表現は “give” と “receive” の2つがあります。一方、日本語には3つありますね。「あげる」「もらう」「くれる」です。
2つしかないものを3つに分けるとなると大変ですよね。これが誤用が発生する理由です。
それではどうやって使い分けるかを見ていきます。
授受において大切なのは「ウチ」と「ソト」の概念です。
「ウチ」とは、話者や話者がより近しいと感じている人のことで、「ソト」とは他人やより距離感のある相手だと思えばいいと思います。
「あげる」は「ウチ→ソト」へ移動が行われる。
「もらう」と「くれる」は 「ソト→ウチ」へ移動が行われる。
この矢印の方向へものや行為が移動します。
上記の例を使って例で見てみましょう。
①(私が)友達にプレゼントをあげた。
②(私が)両親に時計をもらった。
③おじいちゃんが(私に)お小遣いをくれた
①では、私と友達が登場しています。
まず動詞は「あげる」が使われていて、プレゼントは「私→友達」への移動です。
私=ウチ、友達=ソト なので、「ウチ→ソト」になっていますね。
②も同様に考えると、「もらう」で、時計は「両親→私」への移動です。
私=ウチ、両親=ソト なので、「ソト→ウチ」への移動になっています。
③も同様に、「くれる」で、「おじいちゃん→私」への移動です。
おじいちゃん=ソト、私=ウチ で、「ソト→ウチ」になっています。
「私以外」がウチの場合
これまでは「私」が登場していました。
それでは私が登場しない、つまり、第三者間のやりとりではどうなるのでしょうか。
結論から言うと、「もらう」と「くれる」は基本的には第三者間のやりとりには使えませんが、話し手が、ウチ、つまり私に属する人だと思えば使うことができます。
・AさんはBさんにお金を(もらった/くれた)。
という文について、ウチ・ソトの関係をということをわかりやすくするために、言葉を変えてみます。
A=乗客(ソト)、B=私の祖母(ウチ)のとき、
・乗客は私の祖母に席を譲ってもらった。(×)
・乗客は私の祖母に席を譲ってくれた。(○)
1つめの例文は変ですよね。
A=私の祖母(ウチ)、B=乗客(ソト)のとき
・私の祖母は乗客に席を譲ってもらった。(○)
・私の祖母は乗客に席を譲ってくれた。(×)
今度は2つめの例文が変です。
このことを考慮して構文にしてみると、「もらう」と「くれる」について、
「ウチはソトに〜もらう。」
「ソトはウチに〜くれる。」
ということがわかります。
ここで、「あげる」は?と思う人もいるかもしれませんが、「あげる」はちょっと特別です。
基本的には先ほどのように、ウチ→ソトの方向でいいのですが、ソト→ソトでも使うことができる点で、特別です。
・加藤さんは高橋さんに席を譲ってあげた。
・高橋さんは加藤さんに席を譲ってあげた。
どちらでも正しいですね。
まとめ
まとめると以下のようになります。
<授受表現>
①物の授受・・・もののやりとり
②恩恵の授受・・・行為のやりとり
<使い方>
ウチはソトに〜をもらう。
ソトはウチに〜をくれる。
おわりに
授受表現は我々からすると当たり前のように使えていますが、学生にとっては誤用が非常に多いです。
初級で授受を扱うと思うのですが、その学生にウチ・ソトなんて言葉を使ってもわかってもらえるはずもありません。
さらに、敬語を学ぶと、「ていただく、てくださる」にもつながるのので、さらにややこしくなります。
どう噛み砕いて消化するのかというのが、教師としての力量が試されるのかなと思っています。
私もまだまだ力不足な点が多いですが、わかってもらえるような授業ができるように心がけたいなと思います。
参考にした本