ついにこの時が来てしまいました。「音声」です。
音声と聞くと蕁麻疹や寒気などの症状が出てしまう人いませんか。
独学で勉強されている方で音声が苦手な人は特に多いんじゃないでしょうか。
私もその内の一人でした。
養成講座を受けている人ですら、音声が苦手な人は多いです。独学ならなおさらです。
今回は、そんな『音声アレルギー』がどうして起こってしまうのか考えたいと思います。
なぜ音声はわからないのか
自分の経験から考えて、大きく4つの理由があると思います。
一つずつ見ていきましょう。
理由①:用語が多い
「声帯振動がなく、調音点が歯茎硬口蓋で調音法が摩擦音」
「口蓋化すると調音点が硬口蓋の方向へズレます。」
例文のように、音声は普段生きていても聞かないような用語がたくさん使われます。
さらに、音声についてよくわかっていない初期段階にもかかわらず、たくさんの用語が登場します。
聞きなれないことに加え、非常に多くの用語が登場するため、たとえ意味が簡単であっても、脳がシャッターを閉めてしまいます。
玄関先で、小難しい言葉をたくさん使い、商品を買わせようとするセールスマンのようです。
心と玄関のドアを閉めたくなりますね。
理由②:訳のわからない記号が出てくる
次によくあるのが、変な記号がたくさん出てくることでしょう。
記号です。
「æ」や「θ」のような英語の発音の記号を見たことがありますか。
これは英語の「apple」の「a」と「thank you」の「th」の発音です。
「a」は「あ」と「え」の中間の発音、「th」は「下を歯で噛んで出す」なんて教わった発音の記号です。
「æ」や「θ」くらいなら学校の英語で見たことがあるので、なんとか大丈夫だと思う人もいるかもしれません。
しかし、次のこの記号はどうでしょうか?
「ɸ」や「ç」や「ʑ」
音声を勉強すると、こんな記号も知っていなければなりません。
こんな感じの記号が1ページのいたるところに散りばめられていたらどうですか。
本を閉じるのに何秒かかりますか。僕は3秒で十分です。
理由③:どれだけ覚えればいいのかわからない
音声を勉強していると終わりが見えないことがあります。
どのページを開いてもわからないことがあるから、全体像が見えない。
全体像が見えないと、どこが重要かわからない。
どこが重要かがわからないと全部覚えなければと思ってしまいます。
全部覚えなければならないからやる気がなくなります。
こんな負のスパイラルに陥ってしまいます。
電車が何やら止まっているらしいが何の説明もなく、ただ復旧作業中ですと言われるようなものです。
イライラしてしまう。そんな感じに似ている気がします。
さらに試験では大きく3つのパートに分かれているのですが、その内の1つすべて音声の問題となっています。
その量の多さも全体像が見にくくなり、どう勉強していいかわからなくしている原因ではないでしょうか。
理由④:覚えた=点が取れるではない
試験の3分の1が音声に占められていますが、その問題形式はすべてリスニング形式となっています。
音声以外のパートは知識があれば答えを導き出せる問題が多いですが、音声では、知識が前提で、その知識を使って答えを出さなければなりません。
さらにリスニングなので、各問をかなりのハイスピードで処理しなければなりません。
慣れも必要です。
覚えるだけでは足りません。覚えて、洗練させる。
2ステップもあります。
これが4つ目の理由です。
おわりに
以上4つの理由を挙げましたが、これらは複雑に影響し合って音声というものを大きく見せます。
ではこの音声にどうやって立ち向かえばいいのでしょうか。
残念ながら、一瞬ですべて解決する魔法のような方法はありません。
一つ一つゆっくり、理解を進めていくしかありません。
音声の勉強を必要としている人は、日本語が話せる人がほとんどだと思います。
このことが最大のアドバンテージになります。
すでに日本語の発音の知識はまだなくても、日本語を正しく発音できるのです。
ただ知識として覚えようとすると、なかなか頭にも入らないし、すぐに忘れてしまいますが、実際に発音して、知識と発音を結びつけることによって、圧倒的に音声の学習の効率を高めることができます。
そのために、一歩一歩確実に歩みを進めていきましょう。
そのためのお手伝いをしたいと思います。

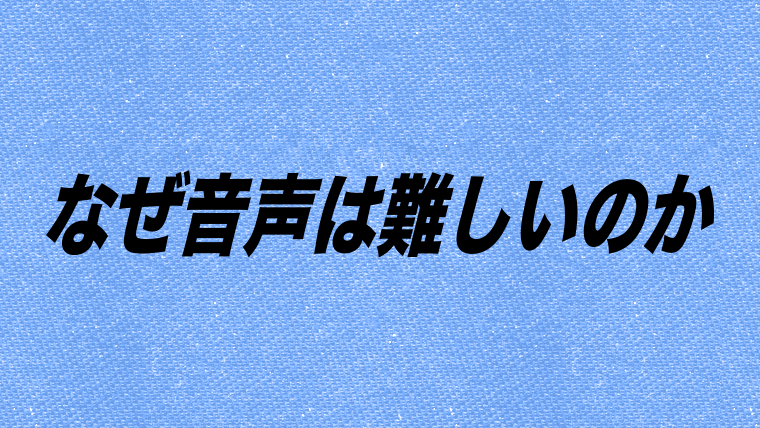
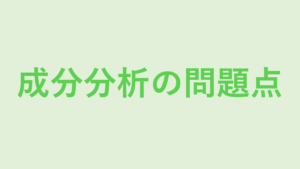
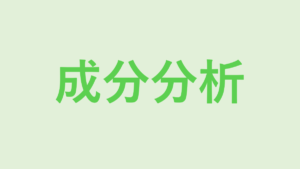
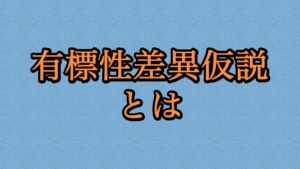

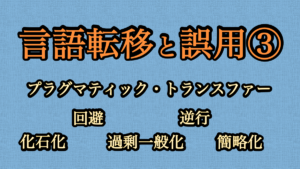
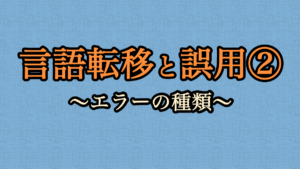
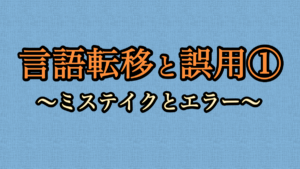
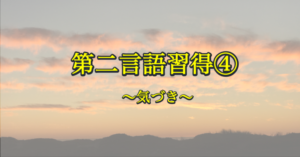
コメント