前回は第一言語習得のスキナーの説からチョムスキーの説を見てきましたが、次はトマセロの説を見ていきます。
トマセロの説
トマセロは前回登場したチョムスキーの説を批判しました。
トマセロの説は、第一言語習得には言語獲得装置ではなく、他者とのやりとりが大切だという説です。
これを用法基盤モデルと言います。
こちらは、認知文法に基盤を置いています。
認知文法というのは、ものすごく簡単にいうと、イメージを関連づけることについての理論のことです。(あとで具体例といっしょに説明します)
用法基盤モデルでは、先ほども言ったように他者とのやりとりがとても大切になってきます。
用法基盤モデルは、他者の意図の読み取り、そしてパターンの発見というのが特筆すべきところです。
他者の意図読み取りというのは、母親が自分を指差しながらママと何度も言うことによって、赤ちゃんが目の前の人はママとなのかと分かるようになるような、注意を共有する能力のことです。
ここではママという言葉(音)と意味(母親本人)のイメージの関連付けています。
パターン発見というのは、家で飼っているチワワをワンワンと呼んでいた赤ちゃんが、散歩中に見かけたダックスフントもワンワンと言ったりするように、カテゴリーを形成する能力のことです。
この赤ちゃんはダックスフントも犬、チワワも犬というイメージの関連付けができています。
このような認知的な能力を駆使して、言語習得が進むというのが用法基盤モデルです。
トマセロの説の補足(領域一般)
チョムスキーのところでも登場した領域固有性に関連して、領域一般という言葉もあります。
トマセロの用法基盤モデルでは、第一言語習得には、領域一般の認知能力が働いていると考えます。
領域一般というのは、言語の領域固有性を認めない立場のことです。
領域一般と領域固有性は反対の立場だということですね。
つまり、
チョムスキーは、認知能力の中の言語能力に注目して、その言語能力(言語獲得装置)によって第一言語習得がされると考えたことに対し、
トマセロは、言語能力だけではなく、他にもたくさんある認知能力を総動員して第一言語習得がされると考えたということですね。
前回のチョムスキーの説とは反対だということがわかりますね。
まとめ
今回のまとめと簡単な流れです。
<トマセロ>
他者とのやりとりが大切(用法基盤モデル)
<批判の流れ>
スキナー ← チョムスキー ← トマセロ
おわりに
第一言語習得では、3つの流れとそれぞれの理論と人物名をおさえましょう。
中には人の名前を覚えるのが苦手という人もいるかもしれません。
最後まで読んでいただいたそんな方々にくだらない語呂合わせをお教えします。
「好き好きトマト」とおぼえましょう。
批判の流れの順番で、ポイントは好きが2回あることです。
「好き(最初の好き→頭にスキがあるスキナー)好き(2回目の好き→おしりに好きがあるチョムスキー)トマト(トマセロ)」とおぼえましょう。
「スキナー、チョムスキー、トマセロ」ということです。
もちろん、トマトの部分を、トマトセロリとか、いい意味にはなりませんが、泊まらせろのような自分の覚えやすい言葉に変換してもいいでしょう。
参考にした本

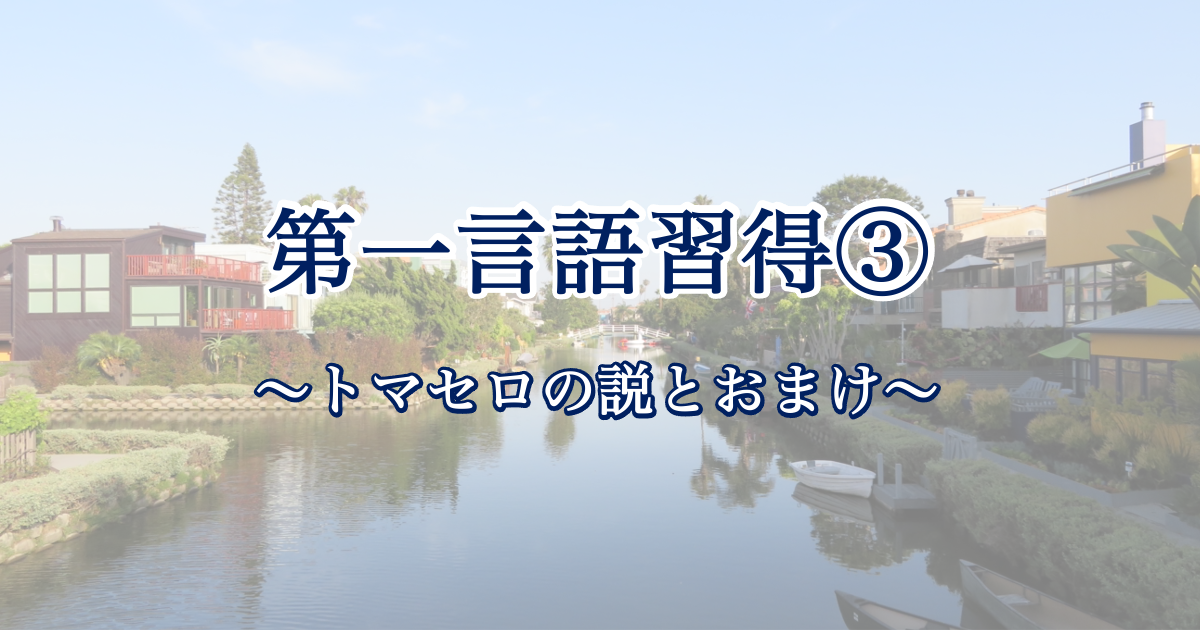
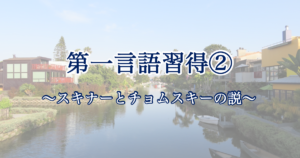
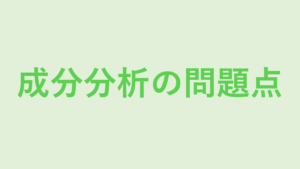
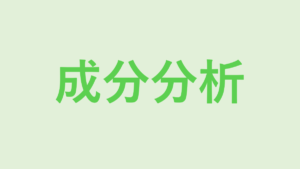
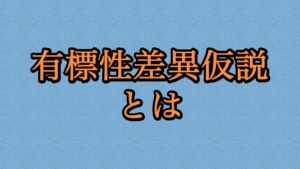
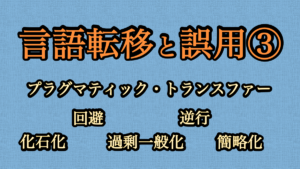
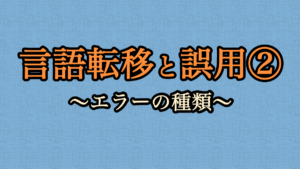
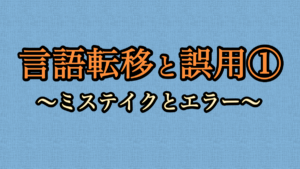
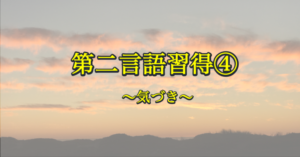
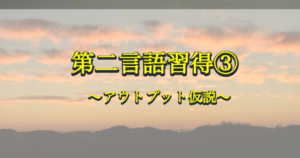
コメント