今回は第二言語習得の2つ目のポイントであるインターアクション仮説についてみていこうと思います。
そもそもインターアクションって何?
まず、そもそも「インターアクション」ってどんな意味なのでしょうか。
インターアクションとはまず英語の言葉です。「interaction」と綴ります。(インタラクションと読まれることもありますが同じ意味です。)
一般的な辞書には、「交流」や「相互」という言葉が意味として載っています。
ですが、もうちょっとだけ具体的にしたいので、英英辞書で調べてみました。
Oxford Leaner’s Dictionariesによると
the act of communicating with somebody, especially while you work, play or spend time with them
と書いてあります。
簡単に訳してみると、「いっしょに働いたり、遊んだり、時間を過ごしたりするような相手とコミュニケーションをとること。」です。
つまり、インターアクションは、「他の人とコミュニケーションをとること」という意味といって問題ないでしょう。
ですから、インターアクション仮説とは、他の人とコミュニケーションをとることで、言語習得がされるという説のことです。
なるほどと思ってしまいそうですが、コミュニケーションという言葉も曖昧です。
なぜなら、コミュニケーションはいろいろなかたちがあるからです。
コミュニケーションは会話だけではありません。言葉がなくてもコミュニケーションは可能なように、コミュニケーションの方法はいくつもあります。
インターアクション仮説で大切になってくるものは、意味交渉というコミュニケーションです。
意味交渉とは、会話中にお互いの発言の内容や意味などを理解できなかったときに、その意味を理解しようとする作戦のことです。
つまり、インターアクション仮説は、相手との意味交渉によって言語習得が進むという説です。
ただし、気をつけておきたいのは、意味交渉をする目的は、意味交渉によって理解できるインプットを増やそうというものなので、言語習得にはインプット仮説の理解可能なインプットが必要だという考えが基本にあります。
ですから、前回のモニターモデルを完全に批判しているということではなく、むしろインプットは大事ですよという立場ではいっしょなのです。
ちなみに、このインターアクション仮説を唱えたのは、ロングという人も押さえておきましょう。
「インターアクションという言葉は長い(ロング)です」と覚えてもいいでしょう。
さて次は、その作戦にはどんなものがあるのかみていきましょう。
ここまでは少し抽象的だったので、具体例も含めながら見ていきますね。
作戦その①:明確化要求
明確化要求というのは、相手の発言がよくわからなかったときに、その発言を理解するためにとる作戦のことです。
会話例をみたほうがわかりやすいと思います。
私 「この前、授業で失敗してしまいましてね・・・。」
若者 「それは草。」
私 「えっ?草?どういう意味ですか。」
この例では、私は、「草」という若者の言葉を理解できていません。
その理解していない状態から脱却するために、どういう意味ですかと明確化の要求をしています。
この意味交渉を経て、私は草という言葉を獲得したことになります。
このように、曖昧であったり、わからないことをクリアに理解したいときに明確化要求がされます。
作戦その②:確認チェック
確認チェックというのは、自分が正しく理解できたかどうか確認するための作戦のことです。
こちらも例でさきほどの続きを見てみましょう。
私 「えっ?草?どういう意味ですか。」
若者 「草っていうのは、笑えるなってときに使うんすよ。」
私 「なるほど、つまりウケるっていう意味のことですね!」
若者 「まあ、そういうことっすね。」
まず、明確化要求によって若者は私に草の意味がわからないことを察知し、草の意味を教えてくれました。
その説明によって私は草の意味がなんとなくわかりました。しかし、その理解をよりしっかりしたものにするために、言い換えることによって確認チェックをおこなっています。
その後相手のフィードバックによって、自分の理解は正しいことがわかりましたね。
作戦その③:理解チェック
理解チェックは、自分が言ったことを相手がちゃんと理解したかを確認する作戦のことです。
こんな例がよくあると思います。
先生 「〜は〜という意味ですからね。みなさん、わかりましたか。」
学生 「はーい、わかりました。簡単です。」
教師は口癖になっている人もいるんじゃないかなと思います。
他にはこんなこともよくあります。
母語話者 「実は、▷★!*%○◆=$〜なんですよね。」
学習者 「(全然なんて言ったかわからないぞ)・・・。」
母語話者 「意味分かりましたか。」
学習者 「(全くわからなかったが)はい。わかりました。」
この母語話者は学習者の理解できていなさそうな反応を感じ、自分の発言がちゃんと理解できたか聞いてくれました。
確認することはいいことなんですが、わかってなくても「はい、わかります」と答えるところまであるあるなので、理解チェックには注意が必要だと思います。
特に日本人は、理解できなくても相手が頑張って日本語を話そうとしているだけで脳をフル回転させて相手の意図を読みとろうとする傾向があるように思います。
しかし、わからないことはわかりませんでしたと伝えることで、今の発言は伝わらなかったと理解できたり、フィードバックなどももらうことができるので、学習者のためになったりします。
フォーカスオンフォーム
今まで見てきた意味交渉の中で共通点に気づきましたでしょうか。
会話の中で、語彙の意味をやりとりによって、わかるようにしていこうとしています。
つまり、会話する時には、特に語彙や文法など気にも留めていません。
しかし、会話をしている最中にわからない言葉(や文法)が登場し、注意がその言葉(や文法)に注意が向き始めます。
この会話の中で文法形式に注意を向けさせることを利用して指導につなげる考えをフォーカス・オン・フォームといいます。
当然、こちらもロングが提唱した考えです。
この考えを利用した教授法がありましたね。
そうです。タスク中心の教授法(TBLT)でしたね。
まとめ
<インターアクション仮説>
意味交渉によって理解度が上がり、言語習得が進むという説
<意味交渉の種類>
①明確化要求 ・・・よくわからなかったことをわかるようにする
②確認チェック・・・自分が理解できたか確認する
③理解チェック・・・相手が理解したか確認する
おわりに
今回は意味交渉の3つを扱いましたが、実際には注意が必要な場合が多いと思います。
明確化チェックや理解チェックでは、学生が使うする分にはいいですが、教師側が何でもかんでも発言内容を推測しながら会話すると、学生側の間違いを見落としたり、途中触れましたがわかっていないのにわかりますという学生もいるので、共に注意が必要です。
一方、個人的には、確認チェックはかなり強力なのかなと思います。教師側は本当に学生が伝えたかった内容をより正確にできますし、学生側は自分の言葉で説明できるからです。ちなみにこれは次回のアウトプット仮説に関わってきます。
そんなわけで、教室内外でも意味交渉はよく使われるので、気をつけられるようになりたいですね。
参考にした本

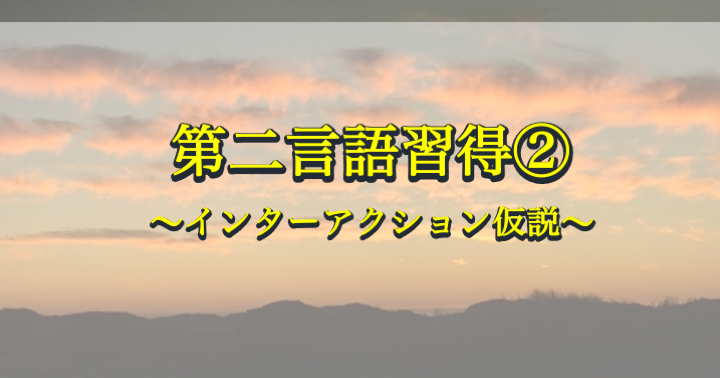
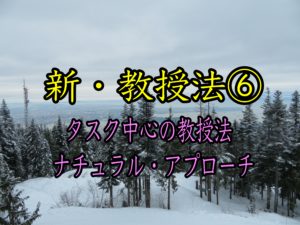
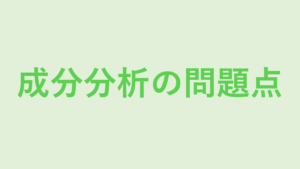
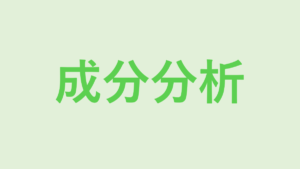
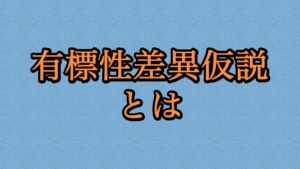
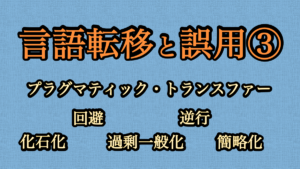
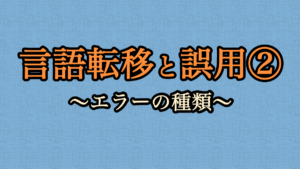
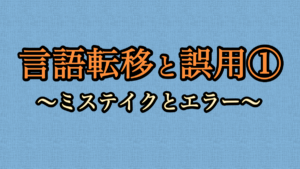
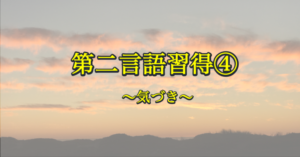
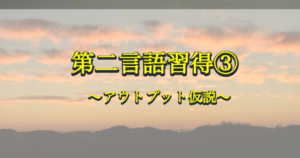
コメント