教養重視だった教授法が批判され、あたらしく登場したナチュラル・メソッド。
これからはどんどんいろいろな直接法が登場してきます。
実はナチュラルメソッドも直説法なのですが、赤本では今回紹介する直接法と分けられています。
今回は二つのビッグなものを紹介していきたいと思います。
それはイギリス系の教授法オーラル・メソッドとアメリカ系のアーミー・メソッドです。
オーラル・メソッド
まず、このオーラル・メソッドはパーマーという人によって作られました。
パーマーはソシュールのラングとパロールの概念に基づいて、言語を「規範としての言語」と「運用としての言語」とに分けました。
簡単に言うと、前者は客観的な言語、後者は個人で使う言葉です。
ややわかりにくいですが、前者がラング、後者がパロールに対応していますね。
そして、パーマーは外国語学習において大切なのは後者の運用だと考え、さらに運用を2つの段階に分けました。
それが「照合」と「融合」です。
難しい言葉が並んでしますが、理解してしまえば簡単です。
照合とは、言葉と意味が結びついている状態で、融合とは言葉と意味がしっかりと溶け合うように結びついていることです。
例えば、単語テストで言葉の意味が出てこなかったけど、なんとか思い出せて解答できたというのが照合の状態で、その言葉の意味を思い出そうとすることなく頭からスラスラ出てくる状態が融合です。
パーマーによると、話せるようになるには照合だけではなく、融合も必要だということです。
私も受験勉強でたくさんの英文法や英単語を覚えましたが、話せるようにならなかったのは照合ができていても融合ができていなかったとなるわけですね。
また、パーマーは言語技能を「聞く・話す」と「読む・書く」とに分け、第一次技能、「聞く・話す」を第一次技能、「読む」「書く」を第二次技能とし、第一次技能の習得を優先したことも大切です。
さてこのようなオーラル・メソッドですが、詳しくみていきましょう。
到達目標
・話せるようになる
実用の教授法なことや、「聞く・話す」を重視している点からもわかります。
教材
・絵カード・レアリア・ジェスチャー
下の練習法のところにありますが、直接法は、文法の導入などを目標言語で行うため絵カード・レアリア・ジェスチャーなどを使います。
現在もあたりまえのように使っています。
練習法
・PPP
・7つの練習活動
PPPとは「Presentation Practice Production」の略で順に文型の導入・提示、基本練習、応用練習のことです。
7つの練習活動とは、第一次技能のための練習法で、
①耳の訓練の練習(音声イメージの形成)
②発音練習
③反復練習
④再生練習(モデルなしで言えるように再生)
⑤置換練習(語の置き換え)
⑥命令練習(教師の命令に従い動作)
⑦定型会話
このように「聞く・話す」ための練習がしっかりしています。また、練習法も現在の教え方にかなり似ています。これは後で触れますが日本の教授法がこのオーラル・メソッドにかなり影響を受けたからです。
長所
・音声接触が多い
上記の豊富な練習法からも納得ですね。
短所
・理解に時間がかかる
時間がかかるそうです。個人的には外国語学習はある程度時間がかかってしまうのは仕方がないと思うのですが、他の教授法よりは時間がかかってしまうということなのかもしれません。
その他
オーラル・メソッドで忘れてはならないのは長沼直江という人です。
パーマーの理論に共鳴し、それを日本語教育に導入し、『標準日本語読本』という教科書も作りました。
長沼によってオーラル・メソッドは日本の教授法に大きな影響を与えました。練習法が今の教え方とそっくりなのはそれだけ長沼のおかげだといえるのかもしれません。
アーミー・メソッド
次はアーミー・メソッドです。ASTPとも言います。こちらはオーラルメソッドと違ってアメリカ系の教授法です。
アーミーというのは陸軍、つまりは軍隊のことなので、第二次世界大戦の終わり頃に作られました。
軍隊の人が外国語を学ぶのは趣味だからではありません。戦時中なので、スパイを養成するためです。
趣味で学習するわけではなく、使える人材を素早く育てたいので、短期間のプログラムになっています。
軍隊のための教授法なので、「厳しい」というのをキーワードにするといいと思います。
行動心理学と構造言語学に基づいている教授法ですが、詳しくはオーディオリンガル・メソッドの回に説明しようと思います。
到達目標
・話せるようになること。
練習法
まず、英語(母国語)と目標言語に精通した人(主に言語学者)による英語での文法などの説明が行われた後、目標言語のネイティブスピーカーであるドリルマスターによる徹底的な口頭練習による暗記をさせます。
少人数のクラスで1日3時間、週に15時間勉強するそうです。
軍隊の教え方なので、とにかく厳しいですね。
学校で暗記するまで繰り返して言わせると確実に学生は嫌になってしまいます。
徹底的な口頭練習という言葉に厳しさを感じます。
教材
・音源
厳しい教授法なので、授業時間以外は自由時間というわけはありません。
まさに合宿で、学習者は同じ宿舎に住み、学習者は外国語の使用が義務付けられていました。
普段から自分でも練習できるように音源が使用されました。
長所
・流暢な話者を輩出できる
すばらしい長所ですね。きつい練習に耐えることができればよさそうです。耐えられればですが。。。
短所
・反復練習は単調
・学習者は過度の緊張
反復練習を厳しくおこなうのでこのような短所も容易に想像ができますね。
まとめ
まとめると以下のようになります。
<オーラル・メソッド>
・パーマー
・「話す」「聞く」の重視
・今とよく似ている教え方
・長沼直江
<アーミー・メソッド>
・軍隊の諜報活動のため
・厳しい
おわりに
いかがでしたか。
パーマーのオーラル・メソッドは正直何を書こうか、どこまで書こうかな悩みました。
練習方法は今とあまり変わらないので、新鮮さは少ないかもしれません。
それはつまり、何を覚えるのか、何が特色なのかがわかりづらいということです。
実際、オーラル・メソッドを大きく取り上げられている教科書じゃ少なく、日本語教育能力検定試験の勉強をしている人には勉強しづらいところだと思います。
しかし、あまり紹介されないパーマーの言語学習の理論は他の教授法にはなかなかみられないものなのです。
オーラル・メソッドは言語学習に対する理論がとても練られています。第一技能の優先や照合と融合の話もその理論の一部に過ぎません。赤本にはあまり書いてありませんでしたが、少しでも印象に残るように触れてみました。
アーミー・メソッドは次回オーディオ・リンガル・メソッドへ発展していきます。
オーディオ・リンガル・メソッドに苦しんでいる人も多いと思いますので、ぜひみてみてくださいね。
参考にした本

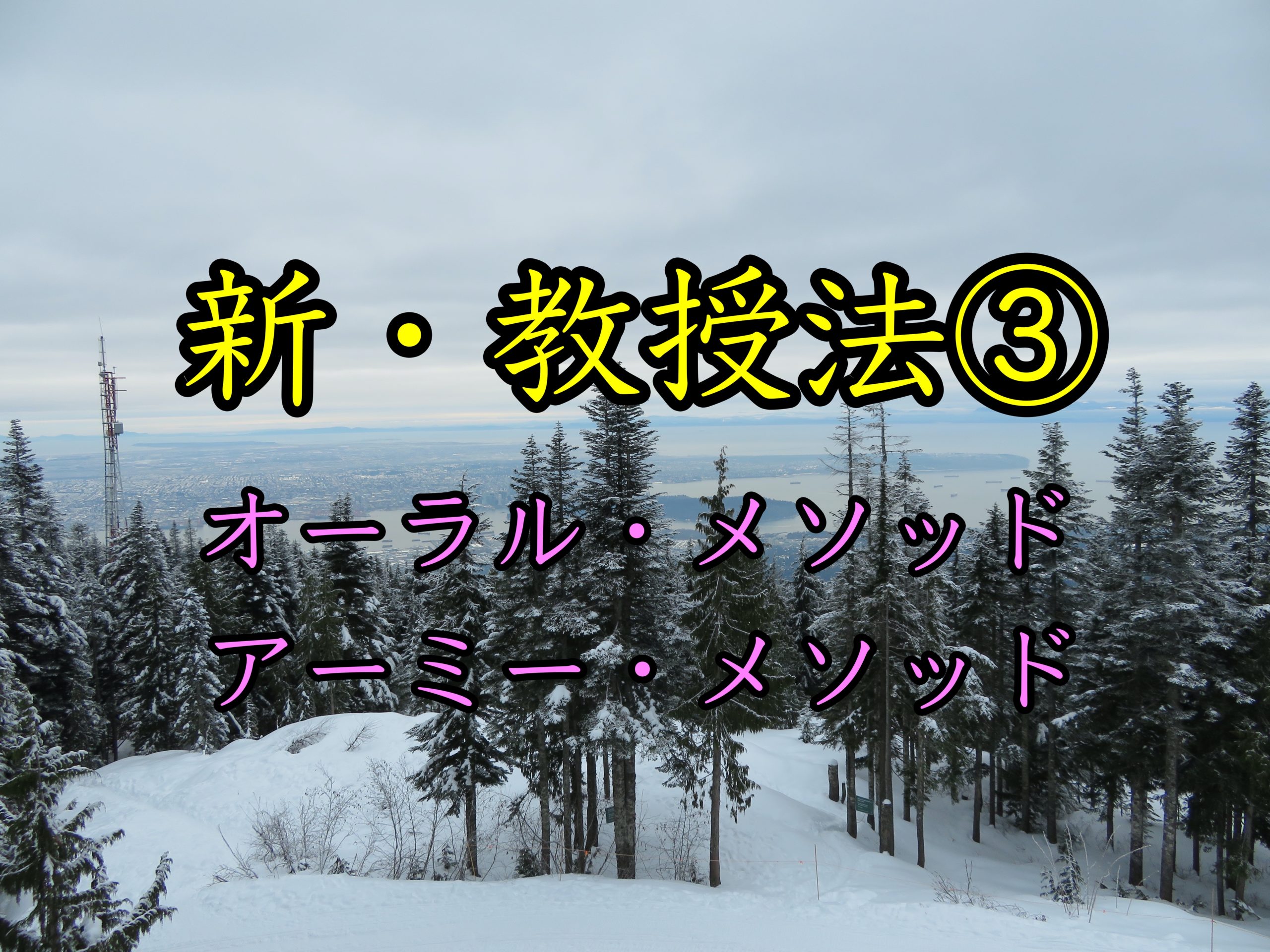
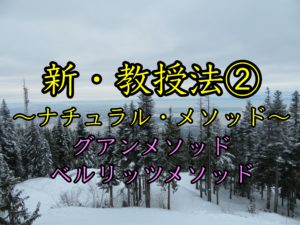
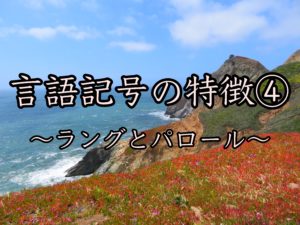
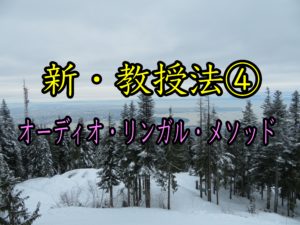
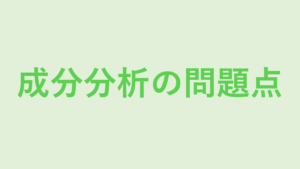
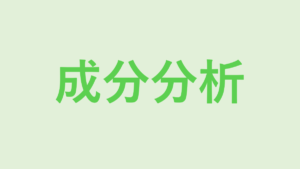
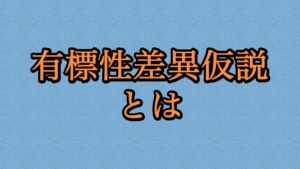
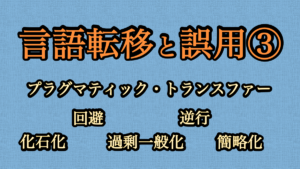
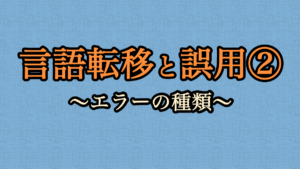
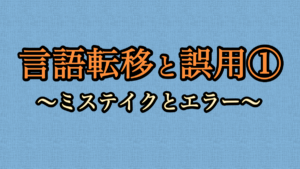
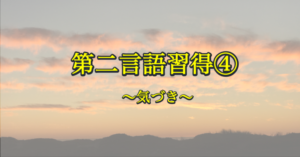
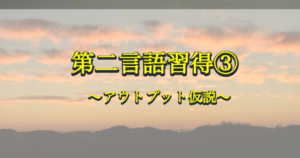
コメント